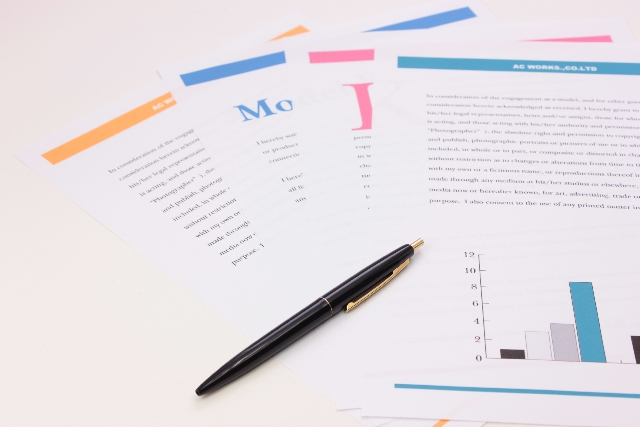


弟の働く会社が(16日)倒産しました。
通常は会社を辞める時に離職票など5種類くらい会社からもらわないといけない書類があると思うのですが(国民年金・健康保険・失業保険
の手続きに必要な書類)、
昨日倒産とのことで、昨日づけで社員全員解雇(200人以上)となってしまいました。
その場合、通常もらえるはずの書類などはどうしたらもらえるのでしょうか?また、書類がなくてもいろいろな手続きはできるのでしょうか?
倒産・解雇の場合、今後どうしたらよいか教えていただけたら幸いです。
弟は今年から社会人として働き出したため、姉としていいアドバイスをしてあげたいのですが、家族もその知識がないため、知っている方、アドバイスお願いできたらと思います。
何卒宜しくお願いします。
通常は会社を辞める時に離職票など5種類くらい会社からもらわないといけない書類があると思うのですが(国民年金・健康保険・失業保険
の手続きに必要な書類)、
昨日倒産とのことで、昨日づけで社員全員解雇(200人以上)となってしまいました。
その場合、通常もらえるはずの書類などはどうしたらもらえるのでしょうか?また、書類がなくてもいろいろな手続きはできるのでしょうか?
倒産・解雇の場合、今後どうしたらよいか教えていただけたら幸いです。
弟は今年から社会人として働き出したため、姉としていいアドバイスをしてあげたいのですが、家族もその知識がないため、知っている方、アドバイスお願いできたらと思います。
何卒宜しくお願いします。
一言で「倒産」といっても中身は色々あります。完全に会社がなくなるのか、新会社に引き継がれるのか、ある事業だけ残すのか..ですが、なくなってしまうとして、
通常は残務整理で人事や総務の仕事はしばらく残るので、退職に関する必要な書類は会社から受け取る事ができるはずです。
また、裁判所から指定された弁護士が社長に代わってそうした事務を仕切るはずです。
当面必要な書類は
①「年金手帳」の交付をうけ、年金を厚生年金から国民年金に切り替えること(市役所),
②「離職票」[雇用保険被保険者証」をもらってハローワークに失業手当の申請と求職申し込みをすること、
③健康保険を国民健康保険に切り替えること(市役所),
④退職日までの今年の賃金支払い証明をもらう⇒ 年末の確定申告用
⑤企業年金や社内預金、生協、共済会などがあればその清算や脱会手続き書類..
自主的な清算で社長や幹部も夜逃げをしてしまっている状況じゃなく、ちゃんと裁判所の決定に基づく「破産」ならば上記のとおりですから会社の指示を待っていればよろしいと思います。心配なら総務の関係者に確認したらどうでしょうか。
通常は残務整理で人事や総務の仕事はしばらく残るので、退職に関する必要な書類は会社から受け取る事ができるはずです。
また、裁判所から指定された弁護士が社長に代わってそうした事務を仕切るはずです。
当面必要な書類は
①「年金手帳」の交付をうけ、年金を厚生年金から国民年金に切り替えること(市役所),
②「離職票」[雇用保険被保険者証」をもらってハローワークに失業手当の申請と求職申し込みをすること、
③健康保険を国民健康保険に切り替えること(市役所),
④退職日までの今年の賃金支払い証明をもらう⇒ 年末の確定申告用
⑤企業年金や社内預金、生協、共済会などがあればその清算や脱会手続き書類..
自主的な清算で社長や幹部も夜逃げをしてしまっている状況じゃなく、ちゃんと裁判所の決定に基づく「破産」ならば上記のとおりですから会社の指示を待っていればよろしいと思います。心配なら総務の関係者に確認したらどうでしょうか。
おそれいります。失業保険、延長申請手続きについておたずねします。
H22/4/30付で1年以上働いた職場(正社員)を自己都合のため退職しました。
理由としては、結婚に伴う引っ越しで家が遠くなったのと、妊娠です。
出産予定日は平成22年10月10日ですので、延長手続きを申請しようと思います。
しかし、6月から退職した会社に引き継ぎ等のため週に1~2回ほどバイトとという形で手伝いに行っています。
できれば、出産ぎりぎりまでバイトに行きたいと考えておりますが、その際、延長申請手続きはいつまでにしなければ
ならないのか教えてください。
また、法律上の産前6週に入ったら延長申請手続きは不可能なのでしょうか?
また、もし、出産後の延長申請手続きというのはできるのでしょうか??
H22/4/30付で1年以上働いた職場(正社員)を自己都合のため退職しました。
理由としては、結婚に伴う引っ越しで家が遠くなったのと、妊娠です。
出産予定日は平成22年10月10日ですので、延長手続きを申請しようと思います。
しかし、6月から退職した会社に引き継ぎ等のため週に1~2回ほどバイトとという形で手伝いに行っています。
できれば、出産ぎりぎりまでバイトに行きたいと考えておりますが、その際、延長申請手続きはいつまでにしなければ
ならないのか教えてください。
また、法律上の産前6週に入ったら延長申請手続きは不可能なのでしょうか?
また、もし、出産後の延長申請手続きというのはできるのでしょうか??
退職&妊娠で失業手当てを延長手続きをしたことがあります。(6年前ですが…)
分かるところだけ回答させてもらうと、
延長手続きは、離職後1ヶ月経過後から1ヶ月以内に申請しないといけません。
(つまりは、退職した日から30日経ち、31日目からから1ヶ月以内)
貴女の場合は、4/30に退職しているので、1ヶ月経過が5/30。
5/31~6/29までの間に受給資格の延長申請をしないといけません。
私がわからないのは…現在バイトをしている事。
失業手当は、雇用保険の被保険者の方が、定年・倒産・自己都合等により離職し
失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し
1日も早く再就職していただくために支給されるもの。
だと認識しているので、バイトしていたら、再就職とみなされるの???
それとも、安定した職ではないから再就職とはみなされない???
バイトを再就職とみなされるなら、バイトを退職してから延長申請が出来る???
そのあたりが良く分かりません。
ハローワークに確認してみてはいかがでしょうか?
分かるところだけ回答させてもらうと、
延長手続きは、離職後1ヶ月経過後から1ヶ月以内に申請しないといけません。
(つまりは、退職した日から30日経ち、31日目からから1ヶ月以内)
貴女の場合は、4/30に退職しているので、1ヶ月経過が5/30。
5/31~6/29までの間に受給資格の延長申請をしないといけません。
私がわからないのは…現在バイトをしている事。
失業手当は、雇用保険の被保険者の方が、定年・倒産・自己都合等により離職し
失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し
1日も早く再就職していただくために支給されるもの。
だと認識しているので、バイトしていたら、再就職とみなされるの???
それとも、安定した職ではないから再就職とはみなされない???
バイトを再就職とみなされるなら、バイトを退職してから延長申請が出来る???
そのあたりが良く分かりません。
ハローワークに確認してみてはいかがでしょうか?
小さな会社で役員になるメリットってなんでしょうか。
現在、社員4名程度の小さな会社を経営しています。
以前、メインで働いていた社員に、取締役に入るか相談したところ
メリットって何かありましたっけ?という反応でした。
社会人自体が少ない為、正直皆経営者目線で数字を見たりしています。
業績があがれば自分の給与もあがるんだと毎年給与も業績見ながら相談しています。
その上で、法的に取締役と登記される事により
1、給与は年棒で動かせない(業績が悪くても下げられない上げる場合は役員賞与なので法人税と所得税の二重課税される)
2、雇用保険等は適用外なので辞めた際失業保険も出ない
細かいところでは取締役会等の書類に押印をする必要があったり。(元々数名の会社なので会議自体が取締役会みたいなもんです)
デメリットばかりが目立って、メリットが無いように思うとの事で、納得してしまいました。
名刺に取締役と書けるのは箔がつくけど、どちらかというと給与をあげたい一心で
経営陣として働いている状況では、1の理由が逆に不便という考えです。
その後、それもそうだなと定款自体を変更し、取締役は私一人にしてしまいました。
他の社会人も役員よりは株式の方が興味がある程度です。
中堅企業になってくると、上下関係をはっきりさせる為ですとか
平社員より高給をもらっても不公平感が無いという点で
取締役は数名設けても良い気がしますが、
数名しかいない零細企業ってこういう感じなのでしょうか。
確かに毎年の業績が読めない為、一旦決めた役員報酬が動かせないのは
私一人でも不便な決まりだなぁとは毎年実感します。
(利益調整できない様にというのは理解しています)
現在、社員4名程度の小さな会社を経営しています。
以前、メインで働いていた社員に、取締役に入るか相談したところ
メリットって何かありましたっけ?という反応でした。
社会人自体が少ない為、正直皆経営者目線で数字を見たりしています。
業績があがれば自分の給与もあがるんだと毎年給与も業績見ながら相談しています。
その上で、法的に取締役と登記される事により
1、給与は年棒で動かせない(業績が悪くても下げられない上げる場合は役員賞与なので法人税と所得税の二重課税される)
2、雇用保険等は適用外なので辞めた際失業保険も出ない
細かいところでは取締役会等の書類に押印をする必要があったり。(元々数名の会社なので会議自体が取締役会みたいなもんです)
デメリットばかりが目立って、メリットが無いように思うとの事で、納得してしまいました。
名刺に取締役と書けるのは箔がつくけど、どちらかというと給与をあげたい一心で
経営陣として働いている状況では、1の理由が逆に不便という考えです。
その後、それもそうだなと定款自体を変更し、取締役は私一人にしてしまいました。
他の社会人も役員よりは株式の方が興味がある程度です。
中堅企業になってくると、上下関係をはっきりさせる為ですとか
平社員より高給をもらっても不公平感が無いという点で
取締役は数名設けても良い気がしますが、
数名しかいない零細企業ってこういう感じなのでしょうか。
確かに毎年の業績が読めない為、一旦決めた役員報酬が動かせないのは
私一人でも不便な決まりだなぁとは毎年実感します。
(利益調整できない様にというのは理解しています)
おっしゃる通りです。
デメリットばかりが目立ちますね。
下手に役員になったら、業績の悪い時に銀行から
融資を受ける際、保証人にされかねません。
少人数のうちは社長の目が届きますから
他に役員なんて必要ありませんよ。
デメリットばかりが目立ちますね。
下手に役員になったら、業績の悪い時に銀行から
融資を受ける際、保証人にされかねません。
少人数のうちは社長の目が届きますから
他に役員なんて必要ありませんよ。
会社が倒産し失業した場合、失業保険の申請や社会保険の変更(厚生年金から国民年金、健康保険から国民保険)の手続きが必要になりますが、その手続きはどうしたらよいのでしょうか?
倒産となれば、会社側は従業員にこれらの申請手続きの為の必要書類(離職証明書や脱退証明書など)を用意する状態でなないでしょうし、最悪の場合、経営者が行方不明になることもあります。そのような場合、どのような手段と手続きによって失業保険の受給と社会保険の変更が出来るのでしょうか?先日勤務先の手形が不渡りになりました。このままいけば倒産失業です。その時に慌てないための予備知識を持っておきたいのです。どなたか教えてください。
倒産となれば、会社側は従業員にこれらの申請手続きの為の必要書類(離職証明書や脱退証明書など)を用意する状態でなないでしょうし、最悪の場合、経営者が行方不明になることもあります。そのような場合、どのような手段と手続きによって失業保険の受給と社会保険の変更が出来るのでしょうか?先日勤務先の手形が不渡りになりました。このままいけば倒産失業です。その時に慌てないための予備知識を持っておきたいのです。どなたか教えてください。
破産管財人の弁護士ですね。
万が一「労働組合」に入っている場合は、労働組合と経営者側との団体交渉ができる場合もあります。
万が一「労働組合」に入っている場合は、労働組合と経営者側との団体交渉ができる場合もあります。
CADの種類についてお尋ねします。
現在失業保険給付受け始めましたが、なかなか思い当たる
職種が見当たりません。
今後の求活に選択肢を広げようと、CADを勉強し始めました。
(以前、ハローワークの求人票に「CADの出来る方」という求人を
観た事があります)
・建築図面の方面だけ練習しておけば良いのでしょうか?
電気関係もあるようですが。
(インターネットでダウンロードしたJW_CADで練習コースもある
内容のものです)
・講習スクールで受講してその後試験を受けて
資格取得した方が有利なのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
現在失業保険給付受け始めましたが、なかなか思い当たる
職種が見当たりません。
今後の求活に選択肢を広げようと、CADを勉強し始めました。
(以前、ハローワークの求人票に「CADの出来る方」という求人を
観た事があります)
・建築図面の方面だけ練習しておけば良いのでしょうか?
電気関係もあるようですが。
(インターネットでダウンロードしたJW_CADで練習コースもある
内容のものです)
・講習スクールで受講してその後試験を受けて
資格取得した方が有利なのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
最初に、40歳手前の若造の生意気な意見だと、断っておきます。また、嫌な意見なのも承知で書き込みをさせていただきます。
もちろん、この手の検定は合格していたほうが有利には違いないんですが・・・・。
質問者様の年齢を拝見する限り、これだけで、就職が有利に働くとは、思えません。
よく書かれているCADが出来る方、って奴。あれ、企業としては、どういったレベルの方を求められていると思いますか?
けして、CADの操作が出来る人じゃないと思います。CADで、図面が引ける人だと思います。ということは、CADプラス何らかの分野の専門知識が必要となるはずなんです。
私自身が、電気の制御盤の仕事をする会社でお世話になっていた時、そこの会社の社長が、ずっとこの手の話してました。
CADはやっているうちに出来るけど、図面に起こすのには、シーケンスとか、そういう知識が必要だから、自分でCADが出来ます、って言う自負を持ちたいのなら、現場をしっかりやれよ、っていうような指導でした。
パソコンが使えます。こういう人は世の中にいっぱいいます。けど、ビジネス文章が作れないんじゃ、ワードの使い方を知っていても意味が無いし、って言うのと同じで、CADはただの道具です。それを活かせるだけの、その他の分野での知識が要ります。
たしかに、JWCADは建築業界では普通に使われています。あと、AUTOCADもよく使われています。
こちらの質問に対する回答としては、図面の練習だけじゃなく、図面になっている対象そのものの勉強・実務経験が必要となります。その上で、やはり、今までの仕事が、そのCADを利用する仕事にどのように繋がって、どのように役立つのか、そういう筋道がたって、それを就職活動という営業の舞台でアピールできないようだと、転職活動の戦略としては、ダメなんじゃないかと思います。
中高年の場合は、新卒者のような、資格を取った、検定に合格した、だから、この仕事に就ける、見たいな話にはならないのは、私より人生経験が長い、質問者様なら分かると思います。その上で、今一度、転職活動について、戦略を考え直すことをお勧めします。
私のオヤジもそうでしたら、中高年齢層の再就職活動が困難を極めるのは想像に難くありません。営業職を長年やられていらっしゃったご様子、であれば、そこから話は膨らみませんでしょうか?
もちろん、この手の検定は合格していたほうが有利には違いないんですが・・・・。
質問者様の年齢を拝見する限り、これだけで、就職が有利に働くとは、思えません。
よく書かれているCADが出来る方、って奴。あれ、企業としては、どういったレベルの方を求められていると思いますか?
けして、CADの操作が出来る人じゃないと思います。CADで、図面が引ける人だと思います。ということは、CADプラス何らかの分野の専門知識が必要となるはずなんです。
私自身が、電気の制御盤の仕事をする会社でお世話になっていた時、そこの会社の社長が、ずっとこの手の話してました。
CADはやっているうちに出来るけど、図面に起こすのには、シーケンスとか、そういう知識が必要だから、自分でCADが出来ます、って言う自負を持ちたいのなら、現場をしっかりやれよ、っていうような指導でした。
パソコンが使えます。こういう人は世の中にいっぱいいます。けど、ビジネス文章が作れないんじゃ、ワードの使い方を知っていても意味が無いし、って言うのと同じで、CADはただの道具です。それを活かせるだけの、その他の分野での知識が要ります。
たしかに、JWCADは建築業界では普通に使われています。あと、AUTOCADもよく使われています。
こちらの質問に対する回答としては、図面の練習だけじゃなく、図面になっている対象そのものの勉強・実務経験が必要となります。その上で、やはり、今までの仕事が、そのCADを利用する仕事にどのように繋がって、どのように役立つのか、そういう筋道がたって、それを就職活動という営業の舞台でアピールできないようだと、転職活動の戦略としては、ダメなんじゃないかと思います。
中高年の場合は、新卒者のような、資格を取った、検定に合格した、だから、この仕事に就ける、見たいな話にはならないのは、私より人生経験が長い、質問者様なら分かると思います。その上で、今一度、転職活動について、戦略を考え直すことをお勧めします。
私のオヤジもそうでしたら、中高年齢層の再就職活動が困難を極めるのは想像に難くありません。営業職を長年やられていらっしゃったご様子、であれば、そこから話は膨らみませんでしょうか?
関連する情報